スター・ウォーズ映画最新作『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』が遂に12/15に公開されました。直前の前評判では大絶賛、大好評でしたが・・これまでにないほどファンの評価が二分してしまっている本作です。
私も個人の感想としては、やはり失望を禁じ得なかったのですが、それでもライアン・ジョンソン監督の革新性はすごいと思っています。それは、何故かといえば、これまで勧善懲悪の物語であったスター・ウォーズを、善と悪をはじめとした物事の調和的な二面性をとらえ、ゴシック文学作品、ゴシック・ロマンス作品として提示することで、新しいスター・ウォーズを作ってしまったからなのです。
さらに、これは映画の中で徹底していて、スター・ウォーズのような大作で、ここまでリスクを恐れず徹底的に新しいことをする大胆さとストーリーテリングの巧みさに驚きます。
そして、まさにその点が評価が二分する原因になっているのですが、さっそく『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』の傑作性をゴシック・ロマンスという視点で考察してみようと思います。
《!以後、『最後のジェダイ』のネタバレ含む。未鑑賞の方は読まないでくださいね》

- はじめに
- ゴシック・ロマンスとは?
- 新三部作にみるゴシック・ロマンス要素の謎
- ゴシック・ロマンスとして解く『最後のジェダイ』の謎
- 二面性から解くキャラクターと脚本の謎
- ゴシック小説的超常現象から解くフォースの謎
- まとめ
- 最後に
- 関連商品へのリンク(Amazon.co.jp)
スポンサーリンク
はじめに
『スター・ウォーズ』は、騎士と姫、悪と善、ロマンス、スカイウォーカー家という高貴な一族の物語であり、SFに見せたファンタジーであり神話である。これは、当然ながら中世騎士物語に原型があって、例えばアーサー王伝説や円卓の騎士の物語は「スター・ウォーズ」の要素になっている。
このブログでも、アーサー王伝説と「スター・ウォーズ」の類似性や考察をしている(スター・ウォーズの謎解き~1~:『フォースの覚醒』新三部作はアーサー王物語だ!類似性から読み解くレイの正体 - StarWalker’s diary)が、今回『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』を鑑賞して思ったのは、ライアン・ジョンソン監督は、この「スター・ウォーズ」の物語を、イギリスで18世紀から19世紀初頭に流行したゴシック小説、特にゴシック・ロマンスとして描きなおした、ということだ。
確かに、スター・ウォーズの世界には、ゴシックが成立する必要な要素が存在していたのだが、はっきりと「スター・ウォーズ」映画の中で、ゴシック・ロマンスとして一つのエピソードを描いた監督は、ライアン・ジョンソン監督が初めてであり、これは画期的なことだ。
そして、『最後のジェダイ』が評価される半面、まったく理解されない理由もまた、ここにあるのだ。
ゴシック・ロマンスとは?
本論に入る前に、ゴシック・ロマンスは何かを書いておこうと思う。私は文学専門家でもないので、私の理解している範囲でだが、この記事を理解いただくために最低限の情報だけを紹介しておこうと思う。ゴシック・ロマンスとは18世紀のイギリスで流行した文学ジャンルを言う。
これは、例えば、古くておどおどとした感じの暗くて不気味なお城があって、そこに、ある日、女性がやってくる。そこでその女性が怪しい事件や、不気味で、神秘的、幻想的な出来事に遭遇したり、それが実は一族の因縁とか、呪われた一族とか原因だったり、地下牢、墓場、幽霊、怪物のようなものが登場して女性が恐怖体験をするような話だ。
これは、その後のSF小説、ホラー小説、推理小説の原型になっていく。
例えば、『フランケンシュタイン』のように人造の怪物が出てきたりすれば、これは科学と結びついてSFになる。19世紀に科学が大きく発展するが、同時にSF小説が出現してくる下地には、18世紀末から19世紀前半までに流行したゴシック小説の影響がある。また、恐怖が中心になると、これはそのままホラー小説であり、その怪奇現象の謎を解く、となると、これは推理小説、ミステリー小説になるといった具合だ。
例えば、私は好きなシャーロック・ホームズの話にも、こういう話が結構ある。
ある若い女の人がいて、その人が例えば大きな館の家庭教師だったりするのだが、その女性が、どうも館の主の様子がおかしい、命を狙われている気がする、といってホームズに事件解決を依頼に来る、という話。これはゴシック小説の系譜の推理小説なわけだ。(『まだらの紐』などはその例だろう。)アルフレッド・ヒッチコックの「サイコ」なんかも、女性が古い洋館に泊まるがそこで怪奇現象におそわれるという話だ。
そして、ゴシック小説は、非常にロマンス的な要素に変化する性質のものがあって、怪奇小説にロマンスが要素として加わったものが、ゴシック・ロマンスなわけだ。
例えば、最近エマ・ワトソン主演で実写化されたディズニーの「美女と野獣」もゴシック・ロマンスの典型だ。ベルという少女が、行方不明になった父親を捜して、森に出かける。その森の奥で古びた如何にも陰鬱な城を発見する。そこで、牢に閉じ込められている父親を見つけるが、恐ろしい姿をした野獣に出会う。ベルは父親が地下牢に閉じ込められているのを助ける代わりに身代わりになりその城に残ることになる。この荒々しい野獣は、実は魔女に姿を変えられていた王子だが、二人の間に徐々にロマンスが芽生えて、野獣が王子の姿に戻るのだ。
このようにゴシック小説にはロマンスが成り立つ性質が隠されている。女性が男性に惹かれる心理も、一見粗野で荒々しいが内面では実は繊細で優しい男だったりする二面性、いわゆるギャップに惹かれるというものがあるし、吊り橋効果でもおなじみだが、怖いという心理や、それが生む緊張やドキドキは、恋愛心理と同じものだからだ。
だから、女性はミステリーを好むし、ホラー映画を一緒に見るというのがデートに良かったり、ゴシック・ファッションが好きな女性がいるのも、こういった要素がゴシック小説、怪奇小説に少なからずあるからなのだ。
そして、『フォースの覚醒』から始まる新三部作にはゴシック小説、ゴシック・ロマンス要素が散りばめられており、『最後のジェダイ』は完全にゴシック・ロマンス作品になっているのだ。
新三部作にみるゴシック・ロマンス要素の謎
なぜ、新三部作の主人公は女の子なのか?
新三部作の主人公、ヒロインは当然レイだ。主人公が女性になったのは、この新三部作が初めだが、この理由も、実は、新三部作がゴシック・ロマンスであるという点から考えると非常にわかりやすい。
なぜなら、そもそも、ロマンス小説というのは、主人公は女性であり女性視点から物語が進むからだ。ロマンスだから、そちらの方がわかりやすい。そして、ゴシック小説では恐怖や怪奇現象に遭遇するのは女性という場合も多いのだ。なぜなら、そもそも女性が恐怖に怖がり、あるいは恐怖にあって狂っていくという過程を書くのがゴシック小説であるからだ。

レイはゴシック小説によく出てくる身寄りのない女の子の設定
だから、ゴシック小説には女流作家がどんどん出てくる。アン・ラドクリフ女史の『ユードルフォの秘密』だったり、クララ・リーブ女史の『イギリスの老男爵』、そして『フランケンシュタイン』『レベッカ』も女流作家によるものだ。あと時代は下るが、アガサ・クリスティー女史もその系譜から生まれた推理作家と言える。
ちなみに、レイ役のデイジー・リドリーは『最後のジェダイ』と同時期に、アガサ・クリスティー女史原作の映画『オリエント急行殺人事件』にも出演していたが、ある一族に起こった悲劇が描かれるという意味で、この推理小説もゴシックの系譜から生まれており、デイジーがこの二つに出演しているのは非常に面白い。
旧三部作は、ルークと父親の物語で、ルークにロマンスは完全になかった。旧三部作ではロマンスは、ハンとレイアのものだった。アナキン三部作では、ジェダイ騎士であるアナキンと女王であるパドメのロマンスを、ロミオとジュリエット、あるいはアーサー王伝説のランスロットと王妃グィネヴィアのような騎士と女王の禁断の恋で描いていた。そして、新三部作は女性を主人公にしたゴシック・ロマンスにしたのだ。
なぜ、レイはイギリス英語を話し、カイロのライトセーバーは赤十字なのか?
これまで「スター・ウォーズ」は善である反乱軍側はアメリカ英語を話し、帝国軍はイギリス英語を話していた。これは、旧三部作に登場する銀河内乱は、大英帝国に対する独立戦争を戦ったアメリカを投影していたからだ。
だから、ルークは農夫であり、ハンはカウボーイ、賞金稼ぎが登場し、レイアだけが帝国(旧共和国)の元老院議員であり、高貴な姫君として登場する。
その意味で「スター・ウォーズ」旧三部作は、勧善懲悪のアメリカ映画の中に、中世騎士道物語と神話の悲劇性の要素を盛り込んだ映画で、舞台はアメリカなのだ。
しかし、新三部作では対局構造は変わっていないもの、その舞台設定は変わっている。『フォースの覚醒』を見ればわかる通り、ファースト・オーダーは完全にナチス・ドイツのイメージで描かれており、レイア将軍率いる抵抗反乱勢力が、レジスタンスと呼ばれるのは、第二次大戦中のナチス支配下のヨーロッパ、主にフランスで地下で反ナチス活動を行っていた「レジスタンス運動」をモデルにしている。
レイアはもはや姫ではなく、将軍として登場する。これは、自由フランスを率いたシャルル・ド・ゴール将軍のイメージだ。
だから、新三部作の舞台設定に近いのは第二次世界大戦中のヨーロッパであって、旧三部作のようなアメリカ独立戦争から変化しているのだ。
だから、新三部作の主人公のレイは、これまでの主人公と違いイギリス英語を話す。デイジー・リドリーはイギリス出身だが、同じく日常ではイギリス訛りを話すジョン・ボイエガ演じるフィンは、劇中ではアメリカ英語を話す。だから、レイ役のデイジーが、そのままイギリス英語を話しているのは意図的演出なのだ。
そして、カイロ・レンが持つ赤いライトセーバーは赤十字だが、これもイングランドの象徴である赤十字のイメージに重なり、ルークのいる惑星オクトーの最古のジェダイ寺院は、アイルランドのスケリッグ・マイケルで撮影されており、ここには古代ケルト人の修道院がある。
このように新三部作には、イギリス要素がかなり強くなっているのだ。もともと、「スター・ウォーズ」は騎士と姫、善と悪、ロマンスとイギリスを始め騎士道文学と相性がいいのだが、今回は更にそれを発展させている。(参考記事:スター・ウォーズの謎解き~1~:『フォースの覚醒』新三部作はアーサー王物語だ!類似性から読み解くレイの正体 - StarWalker’s diary)
そして、これらはまさしく「スター・ウォーズ」を18世紀から19世紀初頭にイギリスで流行したゴシック小説の系譜にのせるための設定でもあるのだ。
なぜ、マズは城に住み、レイは地下牢でライトセーバーを見つけるのか?
マズ・カナタは惑星タコダナの緑の森と湖の美しい惑星の古城に住んでいる。この古城の雰囲気は、中世ヨーロッパの城のようだ。
実は、スター・ウォーズにこのようなはっきりとした城を登場させたのは、『フォースの覚醒』が初めてだ。『ローグ・ワン』ではダース・ヴェイダーの住む城が登場したが、その外観は、マズ・カナタの城のそれとは異なっており、新三部作になるまでこういったイメージの古城は出てこなかった。

古城にやってきたヒロインがある一族の因縁にまつわる話を知る
ヒロインのレイは、この古城にやってくる。そして地下の部屋から自分を呼ぶ声に気がつき、階段を降りていく。そして、そこでルークのライトセーバーを見つけるのだ。
そして、アナキン、ルークと続くスカイウォーカー家の秘密、悲劇、呪われた一族の因縁を知るのだ。「スター・ウォーズ」はスカイウォーカー家の物語なのだか、このスカイウォーカー一族の物語も、非常にゴシック小説の要素と相性がいい。なぜなら、スカイウォーカー家はまさしく呪われた一族だからだ。
選ばれし者、アナキン・スカイウォーカーに始まる銀河で一番高貴な一族だが、アナキン、ベン・ソロと暗黒面に落ちて銀河を恐怖に陥れた者達を生んだ一族であり、ルークにとって悲劇の家系なのだ。
映画を通してみれば、スカイウォーカー家に関わった人間にはろくな運命が待っていない。旧三部作ではルークの育ての親であるオーウェン、ベルー、師匠のオビワンが非業の死を遂げ、アナキンの恋人だったパドメも若くしてこの世を去り、新三部作ではレイアの伴侶であったハンは息子に殺される。ルークなど普通の人間だったら絶望のあまりとうに自殺していてもいいくらいだ。
だから、ゴシック小説に登場する、高貴な一族の因縁、悲劇という要素にぴたりと当てはまるのである。

スカイウォーカー家はまさしく高貴だが先祖の因縁に呪われた一族といえる
レイは、森にある古城で、あのフォース・ビジョンを通じてスカイウォーカー家の呪われた歴史を知り恐れをなして逃げる。そして、森の中で、カイロ・レンに出会い、連れ去られてしまうのだ。しかも、カイロ・レンはレイを、いわゆる「お姫様抱っこ」するのだ。カイロとレイの関係は後述するように『吸血鬼ドラキュラ』のミナとドラキュラを思い起こさせる。
これは、『美女と野獣』を観た人ならすぐわかる類似点で、この映画で描かれているカイロ・レンとレイの物語は、まさしくゴシック・ロマンスの定石を踏んでいる。そして、マズ・カナタの古城は、そのための舞台装置として機能しているのである。
だからこそ、惑星タコダナのマズの城は、湖のほとり、森の中にある中世ヨーロッパ風の城でなければならなかったのである。そしてレイはその古城の地下室で、ライトセーバーを手にすることで、スカイウォーカー家の物語を知る必要があったのだ。
スポンサーリンク
ゴシック・ロマンスとして解く『最後のジェダイ』の謎
なぜ、レイの両親は「誰でもない」のか?
『最後のジェダイ』で、レイの両親は誰でもないということが明らかになった。
正確に言えば、飲み代のためにレイを売ってしまい、レイは完全な非常に強い孤独感をもっている。では、なぜ前作『フォースの覚醒』から色々と憶測を呼んだレイの両親が、誰でもないことになったのだろうか?
実は、これはゴシック・ロマンスという点から考えると非常にわかりやすい。
ゴシック・ロマンスというのは、女性視点から物語が進むことがあるのだが、実はゴシック・ロマンスにおけるヒロインは、身寄りのない女性だったりするのが多いからなのだ。身寄りのない女性であるから、怖がらせやすい。
例えば、『ユードルフォの秘密』は1794年に発表されたアン・ラドクリフのゴシック小説であるが、この小説は、ヒロイン視点で物語が進む。
この話では、エミリーという女性が登場するが、彼女は父親を亡くして孤児になる。そのエミリーは若い男と恋仲になるのだが、この二人の仲を良く思わない義理の伯父が二人の仲を割き、エミリーを城の一室に閉じ込める。そしてそこでエミリーは怪奇現象を経験する…という話だ。
これに限らず、例えば館の主人に雇われた家庭教師とか、身寄りがなくやむなく親近者に預けられた女性とか、そういう女性主人公が多く登場し、古城や大邸宅、古い寺院や修道院に行って恐怖怪奇体験をするのがゴシック・ロマンスだ。
そう考えた場合、レイの両親が誰でもなく、身寄りがないヒロインとするのは、ゴシック・ロマンスの定石であり、当然の帰結だったと言える。
なぜ、ルークの性格を変える必要があったのか?
スカイウォーカー家の物語を知ったレイが向かったのは惑星オクトーの古代ジェダイ寺院だ。そして、そこには悲劇のスカイウォーカー家の血を引く男であるルーク・スカイウォーカーが住んでいる。このルークも、伝説のジェダイと言われながらも、何故かレイを拒み、どうも不気味だ。何を考えているかわからない男として描かれている。
しかも、このルークがレイに見せる顔は少し不気味なのだ。
ファンが首を傾げたシーンの一つに、ルークが海辺に座る謎のモンスターの乳から生乳を絞って飲み干す場面がある。この時レイに見せるルークの顔つきなども、どうも怪しい感じの男にしか見えない。この描写は意図的にそうしているのだろうと思うのだ。
そして、この惑星オクトーの情景は、最初は昼の明るいシーンが多いのだが、だんだん霧が出て、雨になり、雨の降る夜になり、満月の夜になり…と暗い恐ろしい場所のように変化していくのだ。
満月の場面などは、これまでの「スター・ウォーズ」では描かれなかったのではないかと思う。不自然に黒い夜空に大きく輝く月なども、かなりファンタジックな印象を受けるし、雲がかかった細く光る三日月などの描写も、いかにも何かが起きそうな雰囲気を演出している。
この映画で描かれたルーク・スカイウォーカーのキャラクターの変わりようは、多くのファンにとって衝撃だった。いくらなんでもルークがベン・ソロが寝ているところを襲わないと思ったはずだ。しかも、カイロ・レンの語りに出てくるルークの姿はおぞましく、目にも殺気と恐怖が走っており、まったくもってルークと思えない怪奇的な顔をしている。
だが、なんでこんなことをしたのだろうか?
これもゴシック・ロマンスと考えると簡単に謎が解ける。実は、これこそ、ライアン・ジョンソン監督が、『最後のジェダイ』をゴシック・ロマンスとするために必要だった最大のそしてもっとも衝撃的な仕掛けなのだ。
ゴシック・ロマンスでは、ヒロインを狙う者が登場する。そしてこの怪しい者こそが、彼女の親近者だったり、ヒロインに近い者だったり、頼りにしている存在、本来だったら保護者的立場にあたるような人物であるのがまた定石なのだ。
つまり、どうも伯父の様子が私を狙っているようだ・・夫が私を殺そうとしているの・・館の主人が夜中に何やら地下室に行って何かをしている・・とか、そんな感じなのである。本来だったら味方のはずが、怪しいので余計に恐怖心を煽られるのである。
この物語における、ルーク・スカイウォーカーは悲劇のスカイウォーカー家、因縁のある呪われた一族の血を引く男だ。そして、そのルークは本来ならば、レイの保護者的立場になるべき人物だ。つまりジェダイ・マスターであり、レイがフォースの導きをすがれる唯一の人物なのだ。
しかし、なぜかレイを拒否する。ジェダイが滅びるべきと考えている。そして、レイはベン・ソロから衝撃の事実を聞いてしまう。ルークはベン・ソロの力を恐れて彼の寝込みを襲ったというのだ。
このルークがベン・ソロの寝ているところを襲うというのも、いかにもゴシック文学的な怪奇性、恐怖性を持っている。
例えば、ドラキュラ伯爵がミナを襲うのも、ミナが寝ているところであるし、フランケンシュタインの怪物が、ヴィクターの婚約者エリザベスを殺害するのも夜であるし、推理小説では就寝中に殺害することはよく出てくる話だ。先に挙げたホームズの『まだらの紐』でも依頼人のヘレンが殺されるのは就寝中だし、『オリエント急行殺人事件』でも同様だ。 そもそもミステリーでも、怪奇小説でも、事件が起こるのはたいてい夜だったり密室で二人きりだったりと相場は決まっている。
そんなベン・ソロを暗殺しようとした男、ルークは、また同時にレイの力も恐れているのだ。ここに、レイもまたルークという本来は自分の味方で保護者的立場にある人物から、逆に命を狙われるのではないかという恐怖が生まれ、ゴシック小説が成り立つのである。
つまり、レイとカイロ・レンのゴシック・ロマンスが成立するためには、ルークはあのような男として描かなければ成立しなかったのだ。そして、これこそが、ライアン・ジョンソン監督がルークの性格を変えてしまった一番の理由なのである。
なぜ、カイロ・レンとレイは惹かれあうのか?
さて、もう、答えを書いてしまっているが、『最後のジェダイ』の前半は完全にカイロとレイのゴシック・ロマンス小説だ。カイロとレイはフォースで結ばれているのだが、カイロの上半身を見るレイや、お互いに指を触れあう二人など、この描写は完全に恋愛である。
そして、レイはカイロを「ケダモノ」「怪物」と呼ぶ。レイは、カイロが彼の父親であるハン・ソロを殺害する現場を見ている。だが、これに反して、『フォースの覚醒』で描かれたレイとカイロには既に二人がロマンスに発展しそうな要素がたくさんあった。
スターキラー基地に連れ去れたレイは、カイロ・レンに対峙する。
レイはカイロを恐れているのだが、カイロ・レンが仮面を外し、レイが仮面の下のカイロの顔を初めて見る。だが、ここで、レイがカイロ・レンの顔を見た時に、一瞬戸惑った表情を見せる。恐ろしい仮面の下にみた、ハンサムな王子を見たようなどぎまぎし感じを見せるのだ。
そして、レイは、カイロ・レンにさらわれたことで、フォースを通じて、カイロ・レンの心が読めるようになる。今作では、レイは徐々にカイロに惹かれていくのだが、この部分は、ゴシック小説の傑作である『吸血鬼ドラキュラ』や、これを原作としたフランシス・コッポラの映画『ドラキュラ』におけるドラキュラ伯爵とミナ・ハーカーの関係の再現だ。
『吸血鬼ドラキュラ』は、ブラム・ストーカーが1897年に書いた怪奇小説で、ゴシック小説の代表作である。『吸血鬼ドラキュラ』では、ジョナサンという男がドラキュラ伯爵の城を訪ねて行方不明(ドラキュラ伯爵に監禁されてしまう)になるところから物語が始まるのだが、ロンドンにドラキュラ伯爵がやってきて、ジョナサンの婚約者であったミナ・ハーカーを襲う。
そして、ドラキュラ伯爵がミナに血を吸わせると、ミナはドラキュラ伯爵にだんだんと惹かれていくのだ。そして、ドラキュラに心が移ったミナはドラキュラ退治をやめるように言うのだ。また、ミナは催眠術でドラキュラが見えるようになる。
この精神的な結びつきは、原作小説では催眠術だが、『最後のジェダイ』におけるフォースでのレイとカイロ・レンの繋がりは全くこれと同じ展開なのである。
ちなみに、カイロ・レンがレイに「お前は何でもない(You are nothing)」という台詞は、フランシス・コッポラ監督の『ドラキュラ』の中で、ミナ(ウィノナ・ライダー)がドラキュラに「あなたは誰なの?(Who are you ?)」と問いた時に、ドラキュラが答える「私は無なのだ(I am nothing)」と同じである。
また、カイロ・レンが劇中で言う「過去を葬り去れ!殺せ」「それで本当のお前になれる」という台詞も、ドラキュラが、ドラキュラと一緒になりたいというミナに対して「(私と一緒に生きるためには)生まれ変わらなければいけない」というのと同じ意味なのである。
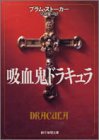
- 作者: ブラムストーカー,Bram Stoker,平井呈一
- 出版社/メーカー: 東京創元社
- 発売日: 1971/04/18
- メディア: 文庫
- 購入: 5人 クリック: 162回
- この商品を含むブログ (60件) を見る
『フォースの覚醒』『最後のジェダイ』では、劇中、レイはカイロ・レンを何度も「怪物」呼ばわりしていたり、マズ・カナタの城ではマズが、城に来襲したファースト・オーダーやカイロ・レンを「けだもの」と呼んでいるように、明らかにゴシック・ロマンスになっているのだ。
怪物と美女が惹かれていくのがゴシック・ロマンスであり、『最後のジェダイ』におけるレイとカイロ・レンは、『美女と野獣』で野獣を見て恐れていたベルが野獣に惹かれることや、『吸血鬼ドラキュラ』でミナがドラキュラに惹かれるのと同じことなのである。
また、先にちょっとだけ紹介した『ユードルフォの秘密』では、孤児のエミリーとその恋人の仲を良く思わない義理の伯父が二人の仲を割く。義理の叔父である伯爵が、ヒロインを怪奇の部屋に閉じ込めてしまうのだ。
もうお気づきだろうが、これは、そのまま『最後のジェダイ』で、ルークがレイとカイロ・レンの中に割り込むあの描写なのだ。
ルークの近くにいながら、一方で隠れてカイロ・レンに惹かれていくレイ。一つの部屋に向かい合って座るレイとカイロの姿は、まさしく本来のレイの保護者的立場にあるルークに隠れて密会している恋人のようだ。しかも、この場合、レイから見たら、ルークはカイロの伯父なのだから義理の伯父に近い立場だ。
そして、ルークはそんな二人を見つけて「やめろ!」と叫んで仲を割いてしまうのだ。完全に『ユードルフォの秘密』と同じ展開なのだ。この描写は、ルークは完全に二人、特にレイからしたら自分の恋を邪魔するお節介もの、邪魔者でしかない。
このゴシック・ロマンスにおけるルークの恐ろしさは 、むしろ10代の女の子の方が理解できるのではないだろうか。
そう考えると、カイロ・レンとレイはこの先どうなるのだろうか?『美女と野獣』では野獣は愛の力で、もとの王子に戻りハッピーエンドを迎える。であるならば、レイはカイロ・レンを転向させ、光に戻ってきたカイロ・レンとレイが結ばれることもありそうだ・・あるいは、ドラキュラのような話になるのであれば、結局、死後、ドラキュラと同じようになることを恐れたミナらにより、ドラキュラが退治されたように、カイロ・レンも退治されることになるのかもしれない・・

カイロ・レンとレイのゴシック・ロマンスの行方はいかに?
スポンサーリンク
二面性から解くキャラクターと脚本の謎
なぜ、キャラクターは二面性を持つのか?
ゴシック小説には、二面性を持つキャラクターが登場する。この二面性というのは、表の顔と裏の顔ということなのだが、一人のキャラクターがまったく違う顔をもつというのはゴシック小説では、怪奇を描くうえでよくある設定だ。
18世紀末から19世紀前半のヨーロッパでは、これまでのキリスト教的教条主義、古典主義から脱却しようとしたロマン主義が勃興するが、同時に神の探求から脱却して、人間精神の探求、道徳哲学が進歩することになる。
19世紀の文学的なモチーフに、自己の二面性というものが登場してくる。わかりやすい例が、ドッペルゲンガーだろう。ドッペルゲンガーという言葉が登場してきたのも18世紀末で、ドイツロマン主義文学の中から出てきた。
この道徳哲学の中に、人間の本来持っている欲望とか感情という側面と、それを抑制する理性と良心、知識といった側面の二つが内在しているという考えが出てくる。そしてそれらはどちらも人間の本性だという考えだ。
そして、この欲望の面が怪物としての顔となり、理性の面が人としての顔となって、一人の人物に内在しているという考えが、ゴシック小説に登場する様々な二面性を持つキャラクターを生んでいく。なぜなら、この二面性は1つの人物の表と裏の顔で、表裏一体なのだが、この二面性が、実はこの人物こそが最も恐ろしい怪物である、というようにミステリー性、怪奇性を生むからである。
このように、自己の分身とか、自己の二面性、二重人格といったものは、まさしくゴシック小説を含む19世紀の文学の中でも取り上げられる概念なのだ。
例えば、『ジキル博士とハイド氏』はその典型だが、『吸血鬼ドラキュラ』のドラキュラも表は紳士だが、裏の顔が吸血鬼という二面性をもつから怪奇小説が成立するのだ。『フランケンシュタイン』に登場したフランケンシュタインの怪物も、優れた知性と人の心を持ちながら、容姿は醜く、フランケンシュタインの友人や妻を殺害する怪物となる。
そして、この二面性の間で、まさしく登場人物は苦悩する。怪物と人間の両方の顔を持つ一人の人物が、自分は怪物であるが、人間の娘に恋をして苦悩する、自分はどちらでもあって、どちらでもない、自分は何者なのか・・・このような二つの顔の間で苦悩するのがゴシック小説に登場する主人公だったりするのだ。

- 作者: ロバート・ルイススティーヴンスン,Robert Louis Stevenson,夏来健次
- 出版社/メーカー: 東京創元社
- 発売日: 2001/08/22
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 3回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
さて、『最後のジェダイ』に登場したキャラクターを見てみると、これらのキャラクターも見事に二面性を持っているのだ。
ローラ・ダーン演じるホルドーは、なにやら高圧的で作戦を持たない一見無責任、無能だがプライドの高い指揮官に見える。しかし、最後はそうでなく、レイアのような慈悲深い、戦略家であり、またレイアと同じようにポーを見守る存在であることがわかる。まさしくホルドーの性格の二面性を描いているのだ。
また、ホルドーと対立するポーもレジスタンスに忠実な優秀なパイロットであるが、今回は命令無視もするし、ホルドーに対してはクーデターを起こすような行動もする。
そして、ベニチオ・デル・トロ演じるDJは、レジスタンスにもファースト・オーダーにも協力する。ファースト・オーダーを倒すために重要な任務に協力したかと思ったら、レジスタンスの存亡にかかわるくらいの秘密をあっさりファースト・オーダーに漏らす。
また、ルークは特に今回は強烈だ。ルークはこれまでの善良な男と、その裏の顔の二面性が描かれている。ライアン・ジョンソン監督は、ジキルとハイドと言ってもいいほどの表と裏の顔の違いを、ルークに与えているのだ。
カイロ・レンは言うまでもない。悪の手先としての表の顔と、一方でレイに惹かれてみせるような善良で繊細な男の裏の顔を持つ。そして、わずかな描写ではあるが、レイも同じように、もはや老人と言っていい歳のルークに対して突然、背後から襲うというくらいに凶暴な一面を描いたり、そもそもカイロ・レンを怪物よばわりしながらも、カイロ・レンに惹かれていくという一見矛盾した心理を描いている。
唯一例外は、レイアとローズ、フィンくらいだろうか。だが、そのレイアは後述するように、今作ではゴシック小説のもう一つのモチーフである「不死者」を演じる役割を与えられている。
キャラクターの二面性を描きたかったために、これまでの「スター・ウォーズ」にあったわかりやすいキャラクター設定とは、今回全く異なってしまっているのだ。
なぜ、紆余曲折の脚本にしたのか?
『最後のジェダイ』で、一番賛否が上がったのが、この紆余曲折の脚本だろう。ホルドーとポーの対立は、結果として不要なものだったし、これによってカント・バイトでのフィンとローズの活躍が全く無駄になった、あの時間は何だったのか?というのはアンチ派の代表的意見になっている。
実は、この紆余曲折の脚本も、ライアン・ジョンソン監督の確信犯だろう。というのも、ライアン・ジョンソン監督がこれが物語の定石でないことくらいはわかるはずだからである。ライアン・ジョンソン監督は、ゴシック文学に現れる物事の二面性というテーマをこの脚本に盛り込んで、あえて正解のない二転三転の物語を作ったのだ。
これまでの「スター・ウォーズ」ではキャラクターの性格や設定ははっきりしており、彼らの行動原理は彼らのキャラクターにしっかりそって描かれていた。旧三部作ではハン・ソロはハン・ソロだし、レイアはレイアだし、ルークはルークでしかなく、二転三転することはなかった。だからこそ、ストーリーもシンプルで直線的で、わかりやすかったのだ。
しかし、この『最後のジェダイ』は全く違うのだ。
キャラクターの個性が二転三転する。だから、物語が紆余曲折する。正しいと思ったことが、間違いであったり、良いと思ったことが、悪い方向に覆ったり。あるいはまた、逆もしかり、という最初から正解のわからない物語に突っ込んでいくのである。
これは、旧三部作や前日譚三部作ではなかったことだ。彼の脚本はキャラクターの持つ二面性、物事の性質の二面性を描くための紆余曲折の物語なのである。だから、最初から正解があってそれに向かっていく直線的な物語では全くなく、それこそがライアン・ジョンソン監督が目指した映画なのだ。
そして、これまでのファンが、この紆余曲折が納得いかないと感じるのも、まさしくこの点が原因なのである。
スポンサーリンク
なぜ、台詞が対句だらけなのか?
そして、ゴシック小説の文学的モチーフである自己の二面性というものは『最後のジェダイ』では登場人物の台詞の中に、対句表現として多数登場する。『最後のジェダイ』を見て気が付いた人も多いと思うが、今回、登場人物がいう台詞は対句のオンパレードになっているのだ。
これらの一見相互に矛盾したように聞こえるこれらの台詞の意味に、首を傾げた人も多いと思うし、これが実はこの映画をより複雑に見せていると思う。
いくつかは日本語訳が難しいので、原文の意味をわかりやすくするため、あえて字幕とは異なり理解のために日本語的には不自然ですが直訳したが、おぼえている範囲で下に例を挙げた。(一部、記憶があいまいで正確ではないかもしれません)
ちなみに、おそらく吹き替えで見た方は、これには気が付かなかったと思う。私も今回1回だけ吹き替えも見たが、吹き替え台詞は、翻訳が難しかったのか、原文の対句表現とは異なる表現になっていたと思う。
・レイがルークに言う。
「ルーク・スカイウォーカーが必要なの」- We need Luke Skywalker.
・ルークがレイに言う。
「ルーク・スカイウォーカーは必要ない」- You don't need Luke Skywalker.
・レイがルークに言う。
「私はどこから来たのでもない」- (I am from)Nowhere.
・ルークがレイに言う。
「どこから来たのでもない者はいない」- No one is from nowhere.
・ルークがレイに言う。
「私はカイロを失った。」
- I failed Kylo.
・レイがルークに言う。
「あなたはカイロを失ったのではない。カイロがあなたを失ったのよ。」
- You didn't fail Kylo. Kylo failed you.
・スノークがカイロ・レンに言う。
「新しいベイダーよ」
- A new Vader.
「お前はベイダーではない。仮面をつけたただの子供だ。」
- You are no Vader. You are just a child in a mask.
・フィンがローズに言う。
「俺はレジスタンスの英雄じゃない」- I am not a Resistance hero.
・ローズがフィンに言う。
「あなたは英雄よ」- You are a hero.
・カイロ・レンがレイ言う。
「お前は何の価値もない」- You come from nothing. You are nothing.
・ヨーダがルークに言う。
「レイが持っているもの以外のものはない」- that library contained nothing that the girl Rey does not already possess.
・レイアもレイに言う。
「我々は必要なものはすべて持っている」- We have everything we need.
・カイロ・レンがレイ言う。
「お前は何でもない、だが私にとっては違う」
- You are nothing. But, not to me.
・レイアがルークに言う。
「息子は行ってしまった」 - My son's gone.
・ルークがレイアに言う。
「誰もどこにも行っていない」- No one's ever really gone.
これらのすべての会話は、自己が何者であるか?に対する問いかけであって、すべてが対句表現になっているのだ。「AはBだ」と誰かが言えば、「AはBではない」と誰かが言うのである。これも自己の二面性、自己の探求への問いかけなのだ。
そして、ファンがこの映画を見て、どうも台詞がしっくりこないと思う理由は、おそらくここにあるのだ。ある人間が、何か抽象的な台詞を言ったと思ったら、別の人間がまた反対の台詞を説明もなくいうので、やはり、ここも従来の「スター・ウォーズ」と全く異なる感覚を抱くのである。
こうしてみると、『最後のジェダイ』は非常に美しい文学作品といえて、意外と小説で読んだほうが面白いかもしれない。
なぜ、ホルドーは特攻するのに、ローズは特攻を否定するのか?
ホルドー中将は、味方のレジスタンスを逃がすため、メガ・スター・デストロイヤーに向かって超空間ジャンプをする。物語冒頭では、ローズの姉のペイジが爆撃機と一緒に犠牲になって勝利を得る。また、映画のクライマックスでは、フィンが同じように自己犠牲のために、ファースト・オーダーの武器に向かって特攻していく。しかし、今度はローズがフィンを止め、これをやめさせるのだ。
この自己犠牲も、じつは『最後のジェダイ』で初めて描かれたものだろう。これまでの「スター・ウォーズ」にはおそらくなかったと思う。デス・スターでも、第二デス・スターでも、スターキラー基地でも、反乱軍は相手の弱点を突く戦術的勝利によって、敵を倒すという戦略的勝利を得ているのだが、これらの作戦は、無謀な作戦ながら、下手な特攻や、他人のための自己犠牲というものはなかった。
キリスト教では自己犠牲というものは愛だとされる。そもそも、イエス・キリストは人類の罪を背負い、人類を救済するために十字架にかかったが、これも自己犠牲だからだ。
この映画は、一方でこのキリスト教的自己犠牲を肯定しながら、一方で否定してみせるのである。しかもローズは、「敵を憎むのでなく、愛するものを救う」ことを説くが、フィンやホルドーは、まさしく愛するものを救うため自己犠牲を行おうとするのだが、ローズは同じ理由でこれを否定するのだ。
ここにも、物事の二面性を描こうとしたことが見て取れる。
なぜ、スノークとメガ・スター・デストロイヤーは二つに別れて終わるのか?
スノーク最高指導者の最後は面白い終わり方だった。ここは映像的にも新しく新鮮で、特にスノークに刺さった真横に伸びたライトセーバーが、すっと画面手前に移動してきて、下から伸びたレイの手に収まる、というのは、非常に斬新な見せ方をしていてとても気に入ったシーンである(物語上、スノークがあっさり殺されるのはどうだろうとは思っているが)。
そして、スノークは、ライトセーバーにより上下真っ二つに割れて死ぬのだ。さらに、その後には、そのスノークの乗っていたメガ・スター・デストロイヤーが左右真っ二つになって破壊される。
このメガ・スター・デストロイヤーの破壊シーンは美しくて私も好きなシーンの一つだ。また無音効果がよく活きていて映像美を作っていた。
これまでの「スター・ウォーズ」に描かれた宇宙船の爆発は、このような描き方はされずただ爆発していただけなのだが、今回は全く異なるのだ。メガ・スター・デストロイヤーとファースト・オーダーの艦隊は、綺麗に左右に裂けて終わる。また、今回のスノークのようなキャラクターの死もこれまでにはなかった。
これらの、何かがこの真っ二つになって倒れていく壊れていくという描写は、すなわち、本来1つであったものが2つの別のものにそれぞれ別れたときに、物事が崩壊するという意味で、物事の二面性の崩壊と、調和的二面性の崩壊によって存在が終わるということを表しているのだろう。
このように、物事の二面性を特に強調したような描写を、この映画では徹底してやっているのがわかる。フォースの光と闇の説明から始まり、キャラクターも、脚本も、台詞も、映像も、メッセージも常に表と裏の二面性を持っている。
この二面性が理解できないと、脚本もキャラクターも一貫性のないものに見えてしまい、一見無駄な展開や、矛盾したメッセージを含んだように見えてしまう。
しかし、この徹底的な調和的二面性の描き方は、ゴシック小説の文学的モチーフと重なり、『最後のジェダイ』で描かれたレイとカイロ・レン、ルークの物語と、すべてのサイドストーリーは、この映画がゴシック小説であるとして考えると、一つの説明で成立しているのだ。
スポンサーリンク
ゴシック小説的超常現象から解くフォースの謎
なぜ、ルークはレイにフォースの二面性を説くのか?
惑星オクトーで、レイはルークに言われて、瞑想する。「何が見えるか」と問われて、この時、レイはこう言うのだ。「光と闇」「生と死」「暖かさと冷たさ」「平和と暴力」そしてその間に「調和(バランス)」があると。これらの言葉も互いに対をなしていて見事に物事の二面性を説いているのだ。

ルークが説く調和的フォースは18世紀末の調和的人間観に基づく
フォースの二面性は、一つのフォースの二つの顔であり、光と闇は別個のものではないことが説かれ、そこにバランスが存在していることが紹介される。これは、もはやこれまで、ジェダイ、シスという勧善懲悪の対立する二面性を描いてきた「スター・ウォーズ」ではない。
そして、これも同じように18世紀末から19世紀前半における道徳哲学の中で唱えられた、人間が持つ感情と欲求に対して、それを制御する理性と良心が内在するという調和的な人間観に通じるものがある。
善と悪というものは、質的に対立する概念でなく、量的な差異があるだけであるというような調和的人間性の考えは、まさしく『最後のジェダイ』における善と悪の調和的なフォース観になっているのである。
だからこそ、あの場面で、レイのあの台詞がわざわざ語られるのである。
なぜ、レイアは宇宙を飛んだのか?
また『最後のジェダイ』をゴシック小説ととらえると、今回登場した様々なフォースの新しい能力の説明がつく。
レイアがフォースで空を飛ぶというシーン。フォースの新しい能力として登場したこのレイアの登場シーンだが、ファンが猛反発したこの突拍子もないアイディアを、なぜライアン・ジョンソン監督が採用してしまったのか?ライアン・ジョンソン監督もこれがファンの反発を招くことは想像できたはずだ。しかし、彼はあえてこれをしたのである。
これも、ゴシック小説を読むように映画を見るとわかる。
ゴシック小説には、幽霊、怪奇現象などが出てくるが、これらの中には「不死者」(undead)と呼ばれる存在が多く出てくる。不死者というのは、生きてもいないし死んでもいないものを表す言葉で、例えば、ドラキュラとか、ゾンビなんかがそうである。
「undead (アンデッド)」という言葉自体が、「吸血鬼ドラキュラ」を書いたブラム・ストーカーによる造語で、まさしくドラキュラのように、死んだものが活動したりする超常現象を指して登場したものだ。あと、フランケンシュタインの怪物もそうだろう。もともと死体をつぎはぎされて作られた人間で、生きてもいないし死んでもいない存在といえる。
今回、『最後のジェダイ』で登場したレイアは司令船から吹き飛ばされて、宇宙空間に放り出される。一見死んだように見えた彼女は、なんとフォースの力で、生きているがごとく、また司令船に戻ってくるのだが、これは、まさしく生きてもいない死んでもいない状態であり、まさしく「不死者」による超常現象なのである。
そして司令船にいるレジスタンスのメンバーは、まるで超常現象を見たように、驚きながらこの光景をみているのだ。白くまた輝きながら、片手を伸ばして戻ってくるレイア。これはまさしく幽霊を見ているような描写なのである。また、空を飛ぶ聖人(flying saint)というのは、キリスト教には昔からある伝承で、今回のレイアがまるで聖人のように、穏やかな顔をして君臨する姿は、まさしく空を飛ぶ聖人(flying saint)を描いているのである。
「スター・ウォーズ」にはフォース・ゴーストが登場するのは、承知の通りだが、実は、このフォース・ゴーストも言ってみれば「不死者(undead)」の概念と同じなのだ。当初、このフォース・ゴーストというものが旧三部作で初登場した際に、ジョージ・ルーカスがそれを意識していたかはわからないが、まさしくそう言う意味では、これまでにも「スター・ウォーズ」にはゴシック小説の要素になるものが存在していたのである。ライアン・ジョンソン監督は、その点に注目して、今回徹底して『最後のジェダイ』をゴシック・ロマンスとして描いてしまったのだ。
レイアが飛んで戻ってくるのは、ライアン・ジョンソン監督によるレイアの「不死者」化であり、「スター・ウォーズ」のゴシック・ロマンス化の産物なのである。
なぜ、レイは惑星オクトーで自分の分身を見るのか?
レイが惑星オクトーで、自分自身の両親が誰か?の謎を解くために闇の穴へと入っていく。そして、レイはまさしく鏡に映った多数の自分の分身を見るのである。
このレイの分身は、まさしくドッペルゲンガーに他ならない。先に少し紹介したが、ドッペルゲンガーというのは、自己の分身が別の場所に現れる超常現象のことで、18世紀末から流行したゴシック小説ではとくに取り上げられた題材である。
レイという自分は何者なのか、という彼女の問いは、そのまま自己の探求であり、この場面は、自分の分身や自己の分裂といったドッペルゲンガーというゴシック小説のモチーフを取り入れているのだ。
そして、この洞窟のシーンは非常に不気味である。これは『フォースの覚醒』におけるマズ・カナタの城の描写に相当する部分で、この洞窟も島の地下にあって、闇に閉ざされているのだ。穴の周囲には黒い草が伸び、なんとも不気味な様相を呈している。
レイは再び、この惑星オクトーという不気味な島にやってきて、この不気味な地下の洞窟にいき、そこで自分のドッペルゲンガーという怪奇現象に遭遇するのである。
これは、完全にゴシック小説の世界なのである。
ちなみに余談だが、この惑星オクトーのシーンは、ほとんどレイと、ルーク、カイロ・レンしか登場しない。チューバッカやR2もファルコン号にいるのに、彼らは全く出てこないのだ。チューバッカはちらっと登場するがストーリーの都合上の必要最低限度の出演に限られている。わざと出番をなくして、カイロ、ルーク、レイの三人の話に絞り込んでおり、この島の怪奇性を強調する作りになっているのだ。
なぜ、ルークはフォースを使って惑星クレイトに現れたのか?
物語後半でルーク・スカイウォーカーは、惑星オクトーにいながらフォースによって、自分自身の姿を惑星クレイトに投影して、カイロ・レンと対峙する。
ルークの新しいフォースの力として、今作で初登場したこの能力だが、この自己の分身を異なる場所にあらわす能力は、いわゆるバイロケーションと呼ばれる。
このバイロケーションは幽体離脱の一種のようなもので、ドッペルゲンガーと似た自分の分身が別の場所に現れる超常現象の類に属する。あくまでもドッペルゲンガーと異なり、自分の意思で分身を発生させることを指すが、このバイロケーションは、スリラーやホラー映画などによく登場するものである。
したがって、ルークが使うフォースの新しい能力でるバイロケーションもまた、ゴシック小説の超常現象に着想を得て生まれたものと思われ、ここにもライアン・ジョンソン監督が描きたかったゴシック小説の世界観が反映されているのだ。
このように、空飛ぶレイアは「不死者(undead)」の概念、惑星オクトーのレイの体験はドッペルゲンガーとの遭遇、ルークの新能力はバイロケーションと、すべてがゴシック小説で取り上げられる超常現象や怪奇現象から着想を得たものになっており、このような従来のスター・ウォーズ世界観とは異なるフォースの能力が生まれた謎もまた、ライアン・ジョンソン監督が徹底してフォースをゴシック小説のモチーフとして描いているからに他ならないのである。
まとめ
さて、『最後のジェダイ』がゴシック小説、ゴシック・ロマンスとした文学作品として書かれていることを説明してきたが、この革新性はやはりライアン・ジョンソン監督の作家性がなければできなかっただろう。
ライアン・ジョンソン監督は、デビュー作の『BRICK ブリック』でフィルム・ノワール的世界観をもったサスペンス、ミステリー作品をつくった人だが、なるほど、だからこそ「スター・ウォーズ」とゴシック小説を結び付けてしまったのだと納得した。
そして、『最後のジェダイ』が、これまでの「スター・ウォーズ」と異なる点は、まさしくこの点であって、これが評価を二分している一番の根本的な要因なのだ。
調和的フォース観、ルークの描き方、紆余曲折の脚本、空飛ぶレイア、キャラクターの性格の一貫性のなさ、善と悪のあいまいさ、二面性などは、そういう意味では表面的な違いにすぎず、根本的な部分で、ライアン・ジョンソン監督の「スター・ウォーズ」が全くこれまでとは別物なのだ。
だから、批評家は大絶賛なのだ。しかし、ファンには大不評なのだ。
そもそも、ゴシック・ロマンス・ファンとスター・フォーズ・ファンは、ファン層があまり被らないだろうと思うので、余計にわかる人は少ないのではないか。
そして、同じ映画ながら評価が二分しているところも、まさしく同じ映画が持つ二面性であって、調和的映画観といえるのだが、作品の評価に至るまでが、その文学的モチーフを捉えているのはなんとも非常に面白い。
個人的な感想を言えば、やはり私には受け入れづらいし、これまでのスター・ウォーズ映画のほうが好きである。また、見ていて前半は良いのだが、後半になると、さすがにこれまでの「スター・ウォーズ」との結びつきがぎこちなくなっていて、この試みが完全にうまくいっていたかというとそうではないのかと思う。
特にルークの描き方は、最後に一転するが、この辺りもいまいち最初のトーンからの変換がうまくないし、さすがにあの旧三部作のルーク・スカイウォーカーの性格から変わり過ぎていて、私には不自然さと違和感しかなかった。
また全体のトーンがダークになりすぎないように苦慮したのか、ユーモア、ギャグ要素をちりばめたが、逆にこれが過剰になっていて、少し抑えめのほうがよかった。特に前半、特にダークな展開が続くレイとルークの裏側で、カント・バイトの物語が進むが、この辺りは、やるならダークトーン一色に近いほうが良かったかもしれない。後半では全体トーンが明るくなるので、逆にユーモアも目立たなくなるが、それなら最初から抑えておいた方が、全体の印象が「スター・ウォーズ」からかけ離れることはなかったのだろうと思う。
しかし、スター・ウォーズを新しい方向にもっていくための試みは必要だし、その意味でライアン・ジョンソン監督の抜擢は、シリーズとして新しい挑戦だっただろう。また、ディズニーにとっては、ゴシック・ロマンスは十八番のジャンルであり、その意味でもスター・ウォーズの新方向をそこに求めたのは自然だったのかもしれない。
最後に
今回は、私も物事の二面性にならって、『最後のジェダイ』の駄作性、傑作性を対にした2本の記事を書いてみました。最後のジェダイは駄作である。最後のジェダイは傑作である。皆様はどのようにご覧になったのでしょう?
ここは賢者オビ=ワン・ケノービの言葉を借りて「見方を変えれば」どちらも正しいことだということかもしれません。
しかしながら、その傑作性は認めても、やはりこれまでの「スター・ウォーズ」的世界観を崩すまでの描写を徹底的にやっている部分は、私はどうしても受け入れられないという感情でいます。この映画の評価は「スター・ウォーズ」がもっとフランチャイズとして長く続いて、旧三部作のファンとかがいなくなった後に、後世になってからもっと高くなるかもしれません。
次回以降は、また『フォースの覚醒』『最後のジェダイ』を合わせて、飽きないスター・ウォーズ関連の考察をしていこうと思います。
エピソード9関連の話や、これまでは取り上げていなかったスピンオフ作品関連も余力があれば記事を書こうと思っています。引き続きよろしくお願い致します。
そして、フォースとともに!
関連商品へのリンク(Amazon.co.jp)

スター・ウォーズ/最後のジェダイ オリジナル・サウンドトラック
- アーティスト: V.A.
- 出版社/メーカー: WALT DISNEY RECORDS
- 発売日: 2017/12/15
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (2件) を見る



